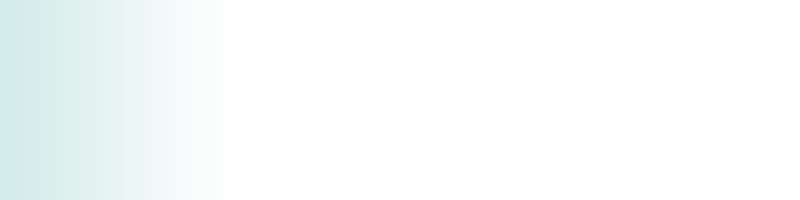支援者を支えるメンタリングの力/今井麻希子さん
支援者を支えるメンタリングの力 ~孤独・孤立に向き合う支援者のための対話~ 実施報告 <後半:スペシャルゲストトーク>
|
「NPOメンタリングプログラム」の2024年度のプログラムが完了し、総括イベントとして、「支援者を支えるメンタリングの力 ~孤独・孤立に向き合う支援者のための対話~」を開催しました。支援を受けた団体の方とメンターとして参加くださった方の経験者トークに加え、スペシャルゲストトークとして、一般社団法人日本NVC研究所 代表理事 今井麻希子さんから見た「NPOメンタリングプログラム」の意義、価値について伺いました。 |
スペシャルゲストトーク/今井 麻希子さん
一般社団法人日本NVC研究所 代表理事/株式会社 yukikazet 代表
経験者トーク
NPO団体(メンティ):「ふれあい交流サロン 南正雀まるっと。」代表 茂上さつきさん
NPOメンタリングプログラム経験者:知香さん
※経験者トークのレポートはこちら
スペシャルゲストトークセッション
ゲスト紹介
今井 麻希子さん
一般社団法人日本NVC研究所 代表理事、CNVC認定トレーナー / コーチ、NVCを軸にした組織開発や対話の場づくりに取り組む。
『「わかりあえない」を越える – 目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケーション・NVC』共訳
https://cnvc.org/trainers/makiko-imai
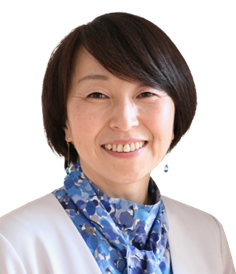 大事なものを明確に、お互いをいかし合う関係を育むNVCが大事にする4つの要素
大事なものを明確に、お互いをいかし合う関係を育むNVCが大事にする4つの要素
――今井さんはどんな活動をされていますか?
私はNVC(Nonviolent Communication)というアプローチを軸に、人と人との関係をより豊かにしていくためのコンサルティングやコミュニケーションのトレーナー、コーチなどの立場で活動しています。一般社団法人日本NVC研究所という団体でNVC大学というプロジェクトを立ち上げて、NVCを学ぶ機会を提供したり、NVCを軸にした組織開発や対話の場作りに取り組んでいます。今回はNVCというテーマがNPOメンタリングプログラム、支援者の活動現場と重なる部分があるということでご縁をいただきました。
NVCとは、自分も相手を大切にするコミュニケーションとして、アメリカの臨床心理士マーシャル・B・ローゼンバーグ博士が提唱したものです。直訳すると「Nonviolent Communication=非暴力コミュニケーション」というやや硬い表現なのですが、誰かを害することのない形でどうやって自分自身や他者と関わりを作っていけるか、そこに着目した手法になっています。例えば、人がぶつかってしまうとき、あるいは自分や相手に厳しくなるとき、こうすべき、という「正しさ」を掲げて、「べき・ねばならない」をぶつけあうことが起こりやすいですよね。そういったときにふと立ち止まって落ちついて物事を見る(=観察)。そしてどんな気持ちが自分の中に、相手の中にあるのかな、というふうに、感情に心を寄せる(=感情)。さらにその奥にある大事にしたい価値や願いは何かな(=ニーズ)というところに関心を寄せて、お互いが喜びからやりたいと思えるような解決策(=リクエスト)を見つけていく。これら「観察・感情・ニーズ・リクエスト」の4つの要素に意識を向けることで、「大事なものを明確にしてお互いをいかし合う」関係を育むことを目指しています。
――NVCはアサーションスキル(※)とは違いますか?
アサーション(※アサーションスキル=自分も相手も尊重しながら自己表現をする、コミュニケーションスキル)と近いなと関心を持たれる方もよくいらっしゃって、似ているなとも言われます。NVCの大きな特徴として、「感情」と「ニーズ」の関係性というものがあります。どんな「感情」の奥にも、たとえネガティブな怒りや悲しみといった「感情」でも、それは本当に大事な願いがあるからであって、その願いがつまり「ニーズ」という概念です。相手のどんな気持ちの奥にも何か大切なものがあると受け止める側面と、相手を非難したいと思うようなときに自分は一体何が大事なのかという、その軸を自分自身で整理した上で会話をしていく。お互いに対話が可能な状態を作っていく上で、「観察・感情・ニーズ・リクエスト」の4つへの意識が非常に重要になっています。それがお互いにいかし合うというところになりますね。
強い思いを持つソーシャルセクターだからこそ必要なもの、持続可能な関係性に向けて
――今井さんのNVCの取り組みは、多くのNPO団体から要望があって研修やワークショップをされているそうね。なぜ、対話やいかし合うこと、受け止めるという、メンタリングとも近いものが今、NPOで必要とされているのでしょうか?
実は私自身もNPOやNGOセクターにいた経験から必要性を感じています。ソーシャルセクターの活動をしていると、私自身もそうだったように、とても強い想いがある。これを達成したい、助けたいという想いは、自分の中の非常に大事な部分から活動しているという背景があります。そして、それゆえに人とぶつかってしまうこともあるんです。自分と異なる考えを持っている人、例えば何かを大切に守りたい人に対して、そんなもの大事じゃないよと意見を言う人がいると、とてもイラッとしたり悲しかったりすることがある。そういう気持ちの衝突によって、活動を継続することが苦しくなるということが、社会活動の現場には多いのではないかと思っています。そして相手に対しての絶望感だとか怒りみたいなことが起こりやすいのと同時に、自分が望むほど成果を出せていないことに対して自分を責めるという気持ちも湧いてしまう。このように、強い想いがあるがゆえに葛藤や自責などが生じるとき、そこにより良い解決策を見いだせることができたら、お互いが感情をすり減らす代わりに、感情を生かしてより良い活動をしていけるのではないかなと思っています。それでNPO、ソーシャルセクターの方からはどうしたらご自身たちが持続可能な形で関係性を健全に保っていけるか、モチベーションを保ちながらこの難しい課題に向き合い続けられるかという観点から、声をかけていただくことが多いです。
――想いが強いからこそぶつかったり感情をすり減らしたりしてしまいがちなところを、どうお互いにケアしながら持続可能にするか。その支援者を支援するような体制や文化は不足していると思いますか?
そうですね。私が感じるのは、やはりNPOの方は対人支援への意識が強いので、他者をケアすることには重きを置かれていますが、一方で自分自身、自分たちのケアがどうしても二の次に置かれてしまいがちです。またNPOとして、他者の非常に重要な情報、機密性が高い繊細な個人情報に触れたりすることもあるわけですから、そこで心が動くことがあって受け止めたとしても、その気持ちを誰に吐き出していいかわからず溜め込んでしまうことがある。そうしたときに、内部でどうケアしていいのかがわからないという現状になっているかなと思います。そこで少しでも、普段思っていることを言葉にできたり、気軽に相談できる環境をつくることで関係性がより深まり、、お互いの理解が深まる。こういった循環を起こしていくような仕組みが、今、強く求められているのではないかと感じています。
――まさに他者への支援という活動だからこそ、自分たち、内部でのケアが不足してしまい、衝突や感情をすり減らす関係が出てきがちになる。そこを内部としてケアしていけるか、仕組みとしてケアしていけるか、今回のNPOメンタリングプログラム含め、今後のテーマとなってくるかと思います。
NPOメンタリングプログラムが個人、NPO、社会へ貢献する3つの意義
――今回のNPOメンタリングプログラム参加者の経験談を聞かれての感想を伺えますか?
経験者お二人の雰囲気がとても和やかで、伺っていて心が温まる思いでした。ちょうど良い距離感というのが、メンターとメンティの間にあるのかなという気がしましたね。内部の方だとお互い聞けない部分があるところを、その団体に関心を持って、心を寄せて聞いてくれる第三者がいることで、素の自分で吐き出せるような、そういった場がそこにあるなと。NPO団体の方の荷物を下ろさせてくれる感覚を受け取りました。
――今井さんにこのNPOメンタリングプログラムをご紹介した際に、メンタリングプログラムの意義を3つ捉えていただきました。その3つの意義についてご紹介いただけますか?
まず、NPO団体のスタッフ本人にとって「抱えこんでしまっている負担を軽くする」という意義です。
社会活動の現場に関わっている方の話を聞くと、抱え込むことが本当に多い。活動に対して本当に真剣に向き合うからこそ、なのですが、そこをほんの少しでも安心して声にしていいんだと思える、声を聞いてもらえたことから自分が本当に辛いなと思える気持ちにもOKと言える、また自分はこれが好きだったんだということを思い出せる。そうすると自分の命が生き生きとしてくるのではないかと思います。そうして自分自身の大事な思いもケアしながら、リソースを消耗することなく、持続可能な活動にしていける。このような点で、第三者の存在、メンタリングプログラムでのメンターがいる意義を感じます。
次に、団体の組織にとっては「団体内でケアし合える仕組みが浸透し、関係性が良くなる」という意義です。
先ほどはメンタリングの個人にとっての意義でしたが、話を聞いてもらい、聞きあっていると、組織の中でも安心して共有し合える雰囲気が出来てきますよね。組織で活動していく中で、安心して吐き出し合えるような場が生まれていくと、些細なことでも物事が深刻になる前の軽い段階で「今、少し聞いてもらっていい?」「ちょっと相談なんだけど」というようにケアし合えることも起こりやすくなってきます。例えば物事が深刻化して、急に辞める方が出てきて初めて状況を知るというのではなく、お互いがケアし合えるようになって、気になることは声に出していいんだっていう安心が広がってくる。それがカルチャーになってくることが、団体にとっての大きな意義ではないかなと思います。
そして最後に社会にとっての意義は、「孤独・孤立の解消につながる活動が増える」ということです。
自分が課題などに向き合ったときに抱えた大変さを声に出せること。「助けて」と言ってもいいかも、反対に自分が何か力になれそうと声をかけられるかも、と今より半歩でも先に踏み出して、相手に届けられるものを、自分が動けるものを見つけること。そこから自分の居場所を作っていけたり、誰かと繋がっていったりするのではないかなと思っています。社会の中で仕組みを作っていくことは大事ですが、仕組みと同時に大切なのは、私達の心のハードルを下げていって、ちょっとでも自分ができることがあるんだっていう実感がつかめる、そんな体験をした人たちを増やしていくこと。それこそが、広い意味で孤独・孤立の解消に繋がっていく活動になるのではないか。自分の人生の中でもそういう活動に少しずつでも取り組んでいけるのではないか、そんなふうに考えています。
――支援しているメンターも、自分には何もできないと思っていたところ、実は少し聞くだけでも、世の中に役立てると実感することで、メンター自身も自信が持てたり、違う一歩が踏み出せたり、そうしてお互いに支え合う社会を作っていくことに繋がっていくと感じました。
社会課題解決に向けて重要な、“縁側”で関わるような心の余白を生む仕組み
――社会にとっては仕組みも、そして私達の心のハードルが下がる体験をする人を増やすことも大事ということで、仕組みに関してはどんなものがあると社会課題解決に向かっていくと思いますか?
仕組み、というと制度としてかっちりしたものが注目されがちですけれど、本当に重要なのは皆が肩書、普段名刺で持っているような顔は一旦脇に置いて、柔軟性のある関わりが持てるような場面だと思います。このNPOのメンタリングプログラムも、サービスグラントさんが提供されるサービスや活動もそういった面が強いですよね。そのような場面をおうちで例えると、縁側のような感じでしょうか。靴を履いたままお茶を飲んだりできるような、そういう関わりが持てるような心の余裕や余白が生まれるような仕組み。そしてそこに時間やリソースを割けることが、社会課題解決に向けては必要になると思います。そのこと自体が明確な成果物を生むわけでも、アウトプットに直結するわけでもないと思いますが、心が重なり合ったり響き合ったりすること自体、目には見えないけれど、世の中にとって非常に大きな需要になるものだと考えています。今まではそこに大きな価値があることを見落としていたかもしれませんが、心にしっかり余白を作る仕組み、そこに向けた取り組みが、社会課題解決にはとても役立つのではないかということです。
――地域社会の課題解決には、目に見える仕組みだけでなく、皆さんで混ざり合うように、心の余白を作りながら力を出し合っていける形を作っていけるといいですよね。ありがとうございました。
支援者を支えるメンタリングの力 ~孤独・孤立に向き合う支援者のための対話~
経験者トークのレポートはこちら ▷
この記事は、ママボノ経験者の森亜希さんに作成いただきました。